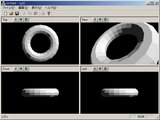« 2006年02月 | メイン | 2006年04月 »
まぁその
ドランク更新なのですが。
ビジネスというくくりと学術というくくりには大きな溝があるわけです。物理的には位置エネルギーが変わらない限りにおいては働いた力は±0なわけですが、現実世界においては自乗平均くらいの資金が動くわけです。それを理解しない頭のいい人が多いわけで、現実世界を知っている人は資金の流れという世知辛い部分に長けているわけです。
それに対してどうこういうのは経済的にウンタラ~とかいう領域に踏み込むわけで、あまり私が好きな領域ではありません。しかし日々の暮らしにおいてその方向に巻き込まれることはあるわけなのですよね。
人類の科学史は自然の模倣に終止せざるを得ないのかもしれませんが(経済的に意味があると言う意味においてという皮肉ですが)、経済に左右されない程度な箱庭の中に早く入れる程度の経済力を手に入れたいと思う次第です。
といっても、外界からの意味のある刺激という意味では「WAR GAMES」ですら、人類を相手にしている分においては「アクション」そして「リアクション」の繰りかえしと仮定できます。人間の行動はその範囲において想定が可能ですが、自然という世界(勿論数学的世界を含めて)を相手にする分には、その範囲は今までの想像を越える世界を相手にしなければなりません。
ドランカーの望みとしては自然の全てを見たいのと同時に、それが達成された世界の趣の無さに興味の幻滅を感じざるを得ません。人間の感情は置いておくとして、科学的に解明された世界を科学者が興味をもって生きることができるかどうかが気になってしょうがありません。それは、音楽的に言えばあらゆる作曲がなされ尽くし、自分は作曲家にはなれず演奏者としての世界しか存在し得ない世界をあらわします。私は科学的にそんな世界があらわれたとき、生きる意味を見出せる気がしません。謎の無い世界は趣が無さ過ぎます。
そしてこれはきっと人間のエゴなのでしょう。いじめのない少年時代が無いように、科学的な謎の無い世界は存在しえません。勿論その前提として「人間にとって」という制約が付くことを、人類の歴史が続く限り、誰も証明することと実践することはできないと確信しますし、仮にそんな世界ができた場合、それは人類とは別の種であると規定すべきであると私は思います。
経済的~という魔法の言葉は、人類相手に対してのみ、その魔力を発します。
2006年03月09日
CATALYST 6.3
3.8 付けで RADEON 系の新しいドライバがリリースされました。
https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=640
CATALYST 6.3 Modified: 3/8/2006
2006年03月08日
小西真奈美の今日の大丈夫。
当たってしまいましたv すっかり忘れていた頃にこういった懸賞ものって届きますね。
登録したエントリは 2006.10.04 なので、もう 5 ヶ月も前になります。DVD には撮影風景や NG 集などもあり、本編よりそっちの方がおもしろいです。本編は「~~、大丈夫。」が繰り返されるだけなので、それほどおもしろいというわけではありませんし・・・。
現在 DTI では 小西真奈美のおてがみムービー「ハル、クル、サイクル」 というキャンペーンをやっているようです。コンセプト的には「今日の大丈夫。」と同じようなショートムービーを使ったメッセージ映像です。
残念ながらというか、空は曇天です。こんな感じですね。今の季節(冬)に撮影をしているなら空気が澄んでいるはずだと思うのですが、いつ撮影を行っていた(現在も行っている?)のかが気になります。天候ばかりはなんともできないのが撮影の難しい部分です。
前回も書いていますが、なかなかドラマ出演がありませんね。春クールはどうなんでしょう。
2006年03月07日
坂の上の雲(3)
この巻の冒頭、子規がその生涯を閉じます。3 巻の 9 割に子規はあらわれません。しかし時間は間断なく進ませねばならず、司馬さんはこの小説の書き方を「まだ悩んでいる」と記述します。正岡子規のこの小説で果たした役割に関しては全巻を読み終わった後でまた考えてみようと思います。
この巻ではついに日露戦争が開戦を迎えます。内容は陸海における戦闘に関するものが増えるため、必然的にそれを昭和の太平洋戦争史に結びつける部分が散見できます。日露戦争を読むと同時に作者の太平洋戦争史観を読むことができます。
ついでながら、好古の観察には、昭和期の日本軍人が好んでいった精神力や忠誠心などといった抽象的なことはいっさい語っていない。
すべて、客観的事実をとらえ、軍隊の物理性のみを論じている。これが、好古だけでなく、明治の日本人の共通性であり、昭和期の日本軍人が、敵国と自国の軍隊の力をはかる上で、秤にもかけられぬ忠誠心や精神力を、最初から日本が絶大であるとして大きな計算要素にしたということと、まるでちがっている。(p133,134)
たとえていえば、太平洋戦争を指導した日本陸軍の首脳部の戦略戦術思想がそれであろう。戦術の基本である算術性をうしない、世界史上まれにみる哲学性と神秘性を多分にもたせたもので、多分というよりはむしろ、欠如している算術性の代用要素として哲学性を入れた。戦略的基盤や経済的基礎のうらづけのない「必勝の信念」の鼓吹や、「神州不滅」思想の宣伝、それに自殺戦術の賛美とその固定化という信じがたいほどの神秘哲学が、軍服をきた戦争指導者たちの基礎思想のようになってしまっていた。
この奇妙さについては、この稿の目的ではない。ただ日露戦争当時の政戦略の最高指導者群は、三十数年後のその群れとは種族までちがうかとおもわれるほどに、合理主義的計算思想から一歩も踏みはずしてはいない。これは当時の四十歳以上の日本人の普遍的教養であった朱子学が多少の役割をはたしていたともいえるかもしれない。朱子学は合理主義の立場に立ち、極度に神秘性を排する思考法をもち、それが江戸中期から明治中期までの日本人の知識人の骨髄にまでしみこんでいた。(p196,197)
戦術の要諦は、手練手管ではない。日本人の古来の好みとして、小部隊をもって奇策縦横、大軍を翻弄撃破するといったところに戦術があるとし、そのような奇功のぬしを名将としてきた。源義経の鵯越(ひよどりごえ)の奇襲や楠木正成の千早城の篭城戦などが日本人ごのみの典型であるだろう。
(中略)
日本の江戸時代の史学者や庶民が楠木正成や義経を好んだために、その伝統がずっとつづき、昭和時代の軍事指導者までが専門家のくせに右の素人の好みに憑かれ、日本独特のふしぎな軍事思想をつくりあげ、当人たちもそれを信奉し、ついには対米戦をやってのけたが、日露戦争のころの軍事思想はその後のそれとはまったくちがっている。戦いの期間を通じてつねに兵力不足と砲弾不足になやみ悪戦苦闘をかさねたが、それでも概念としては敵と同数もしくはそれ以上であろうとした。海軍の場合は、敵よりも数量と質において凌駕しようとし、げんに凌駕した。(p285,286)
「秋山がああいってくれてたすかった」
というのは、のちに軍の幕僚たちがいったところだが、欧州式でいえば騎兵旅団の機能としてそれが当然な着想なのである。ちなみに日本陸軍の首脳は、この時代における騎兵、のちの時代における捜索用戦車や飛行機といったふうな飛躍的機能をもつ要素をつねにつかいこなせないままに陸軍史を終幕させた。日本人の民族的な欠陥につながるものかもしれない。(p311)
が、日本軍の基本思想は、そのような「陣地推進主義」ではなく、大きな意味での奇襲・強襲が常套の方法であった。拠点をすすめてゆくどころか、拠点すらろくにない。兵士の肉体をすすめてゆくのである。当然、戦術は指揮官と兵士の勇敢さに依存せざるを得ない。ときには戦術なしで、実戦者の勇敢さだけに依存するというやりかたもとる。のちの乃木軍(第三軍)の旅順攻略などはその典型であり、このほとんど体質化した個癖は昭和期になっても濃厚に遺伝し、ついには陸軍そのものの滅亡にいたる。(p315)
司馬さんが太平洋戦争に関する小説が書けなかった理由は、この傾向にあるのかな、とふと思いました。未来から過去を俯瞰するという傾向です。太平洋戦争当時と現在に関して、国の首脳部を比べる、前線の兵の心理を比べる、等々。実体験として兵士であったために小説として仕立てることができなかたのかとも思います(司馬さんに関してはまだまだ知らない部分が多すぎるのであまり踏み込んではかけませんが、知らなかったときの直感として記しておきます)。「この国のかたち」を次に読むときは新しい感覚で読むことができる気がします。
さて、この巻では薩摩的将帥の総括的な記述を読むことができます。
人物が大きいというのは、いかにも東洋的な表現だが、明治もおわったあるとき、ある外務大臣の私的な宴席で、明治の人物論が出た。
「人間が大きいという点では、大山厳が最大だろう」
と誰かがいうと、いやおなじ薩摩人なが西郷従道のほうが、大山の五倍も大きかった、と別のひとが言ったところ、一座のどこからも異論が出なかったという。もっともその席で、西郷隆盛を知っている人がいて、
「その従道でも、兄の隆盛にくらべると月の前の星だった」
といったから、一座のひとびとは西郷隆盛という人物の巨大さを想像するのに、気が遠くなる思いがしたという。隆盛と従道は前記のとおり兄弟だが、大山はいとこにあたる。この血族は、なにか異様な血をわけあっていたらしい。
この三人が、どうやら薩摩人の一典型をなしている。将帥の性格というか、そういうものがあるらしい。
薩摩的将帥というのは、右の三人に共通しているように、おなじ方法を用いる。まず、自分の実務のいっさいをまかせるすぐれた実務家をさがす。それについては、できるだけ自分の感情と利害をおさえて選択する。あとはその実務家のやりいいようにひろい場をつくってやり、なにもかもまかせきってしまう。ただ場をつくる政略だけを担当し、もし実務家が失敗すればさっさと腹を切るという覚悟をきめこむ。かれら三人とおなじ鹿児島城下の加治屋町の出身の東郷平八郎も、そういう薩摩風のやりかたであった。(p50,51)
このとき西郷従道は海軍大臣を務めており、実務家として山本権兵衛を起用することになります。
「なにもかも思うとおりにやってください。あんたがやりにくいようなことがあれば、私が掃除に出かけます」
と言い、権兵衛の改革が急務で八方から苦情がでたときも、西郷はその一流のやりかたで適宜に政治的処理をやってのけた。(p51)
ちょっと次巻の先読みが進んでいるため、布石的に以下の引用をしておきます。
戦艦三笠を英国のヴィッカース社に注文したのは明治三十一年であったが、しかしこの時期すでに海軍予算は尽きてしまっており、前渡金を捻出することができず、権兵衛は苦慮した。
このころ権兵衛は四十七歳で、海軍大臣をつとめている。
当時、西郷は内務大臣をしていた。
(中略)
権兵衛は万策つきた。西郷になにか智恵はないものかと訪ねると、西郷は事情をききおわってから、
「それは山本サン、買わねばいけません。だから、予算を流用するのです。むろん、違憲です。しかしもし議会に追及されて許してくれなんだら、ああたと私とふたり二重橋の前まででかけて行って腹を切りましょう。二人が死んで主力艦ができればそれで結構です」(p64,65)
これは日本的官僚主義とは真逆の位置に存在します。
最後に、私がこの巻のさわりだと感じる箇所に関して。それは日本がロシアに対して開戦を決意するに至る経緯に関してです。ページ的には 176~180 となります。日露戦争の開戦を決意するに至る部分の記述を読んだときには、太平洋戦争に至る「ハルノート」を思い出さずにはいられませんでした。そしてそれを思った次のページに、果たしてこのことが記述されていました。ここには 20 世紀に至るまで続く人種差別的要素に関する言及も含まれています。ある種、今まで読んできた司馬小説とは趣を異にしている箇所だと感じます。
毎巻思いますが、この小説は大変おもしろいです。NHK は 2008 年にスペシャル大河として放送するために現在製作を行っているとのことですが、どんな作品にしあがるのか。大変興味深いです。
2006年03月06日
2006.03.06
ITmedia News:米Silicon Graphics、従業員250人を削減
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0603/04/news008.html
グラフィックスの分野の経営って難しいですねぇ。3DLabs, Silicon Graphics に続くのはどこか。NVIDIA, ATI にしても数年後にはどうなるかわかりません。
ITmedia エンタープライズ:情報流出事件多発でWinny接続数はむしろ「増加」
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0603/03/news119.html
「Winnyのネットワークにつながっているノード数は平日で30万強、休日になると40~45万ノード」ということですが、意外と少ないなというのが感想です。海外の P2P ソフトも含めた P2P ノードマップのようなものの研究をすすめておけば、今後の P2P 大航海時代((c)ナデシコ)の主導権が握れそうですね。web の検索技術が現在ホットであるように、P2P の情報検索が後の時代のトレンドになっていくかもしれません。どちらも同じくフィルタリング技術といえます。そういう意味では企業の企画室や企画屋などと呼ばれる人たちは市場のニーズをフィルタリングする存在といえますね。
「2006年中のSEDテレビの発売には反対」,東芝の藤井常務 - FPD International - Tech-On!
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060306/114132/
液晶や PDP などの画質と現在のブラウン管(SEDもこれに入るはず)の画質を議論する際に必ず思い出すことに、お菓子の話があります。厳密な名称を忘れてしまっていて出典に関していろいろ調べていたのですがなかなか見つからないので間違っていると思いますが、昭和初期(?)のお菓子の原料にはチリコ(?)だったかチコリ(?)だったかという原材料が使われていたものがあったそうです。それが使われているお菓子はとてもおいしいのですが、人体に影響があるということで規制され、ある年を境にそのお菓子が食べられなくなりました。そのお菓子の味を知っている人は「やはりチリコ(?)入りのお菓子には勝てない」とその後のお菓子を評したようです。
もちろん規制以降のお菓子しか食べたことのない人にはその味が普通であるので規制以前の味はわからないのですが、今後液晶や PDP が更に普及してブラウン管の映像を知らない人たちが現れたとき、その人たちは本当のソース映像の美しさを見ることはできないんだな、と思ってしまいます。
しかしこれにしたって相対的なもので、性能の悪いブラウン管 TV と性能のいい液晶 TV ではどちらが美しいか、といった取り留めも無い議論となってしまうことは確かです。美しさの基準は主観的なものですし。
2006年03月05日
とりあえず mqo 表示
Metasequoia と Mikoto を使うことに決めたので、まず mqo のローダと表示ツールの作成です。VC8 も入手できたので慣れる意味もあって CSplitterWnd を使ったアプリとして組んでいます。最近はアプリ系は組んでいなかったり(といっても以前もそれほど組んでいたわけではないか…)、MFC もまじめにやったことがなかったりで、ウィンドウの制御部分がはまり気味です。やっぱり必要なのはリファレンスよりサンプルですね。習うより慣れろ。
平行して Mikoto がどういったソフトであるかも確認したのですが、意外とおもしろいソフトでした。Metasequoia のモデルデータに意味を持たせ、ポリゴンとラインを組み合わせることによって親子関係を持つボーンを組むことができます。ちょっと調べただけなので認識に間違いがあるかもしれませんが、モデルデータの親子関係は無理そうです。まぁボーンがあればなんとでもなるので問題はないですね。それに実はできるのであればそれはそれで OK ですし。特に単一ファイルになるので意外と楽かもしれません。
Mikoto は残念ならがここ 3 年半ほど更新がされていないようです。もともとは IPA の未踏ユースとともに成長したソフトのようです(この成果(ドキュメントとソースコード)って一般に公開されないんでしょうかね?) 「Metasequoia Mikoto」 で検索すると 453 件なので、それほど普及しているというわけでもないのかな、と思います。Mikoto を知る前は Blender を使おうとも思ったのですが、これは Mikoto でつまったらまた考えることとします。
現在は Metasequoia の頂点データとそれから面法線の作成、表示までが完了。あとは頂点法線にして、テクスチャをサポートして、Mikoto フォーマットを調べて、って感じですね。mqo + Mikoto ファイルだけなら特に 3 面表示はいらないのですが、以前からやろうと思ってたのでいい機会だと思い 3 面 + perspective な表示にしてみています。
きまり
「いつも、おなじ時刻にやってくるほうがいいんだ。あんたが午後四時にやってくるとすると、おれ、三時には、もう、うれしくなりだすというものだ。そして、時刻がたつにつれて、おれはうれしくなるだろう。四時には、もう、おちおちしていられなくなって、おれは、幸福のありがたさを身にしみて思う。だけど、もし、あんたが、いつでもかまわずやってくるんだと、いつ、あんたを待つ気もちになっていいのか、てんでわかりっこないからなあ……きまりがいるんだよ」星の王子さま ISBN:4001156768 (p97,98)
だれもが子どもの頃に一度は { 読んだ | 読んでもらった } ことがあるであろう「星の王子さま」です。一番好きな部分がこの fox のセリフです。
このきまりは、例えば blog の更新であったり(笑)は一番わかりやすいでしょうか。ある blog のファンだったら更新を楽しみにしていて、決まった時間に見にいったりするでしょう。生活に関して例えると、通勤通学などの電車があてはまりますね。決まった時間の電車にのってくるまだ知り合いではない人が気になる場合などはこれにあたります。また飲食店などに客としていく場合には { 従業員 | アルバイト } のシフトを気にしたりや、自分がサービスをする側である場合には、いつも同じ時間に来るお客さんなど、様々なケースがあると思います。
ゆるやかな制約がそこに存在して、それを回避することが可能であるにもかかわらずそれに制約されること、が必要条件になります。授業や習い事などで時間割や担任が決まってしまった場合には、これは適用されなくなると思います。これはあまりにも強制力が強すぎるので。
自然界における現象はまた難しいですね。日の出日の入りなどはきまっているので適用外にしたくなりますが、四季の移り変わりはこれに入れたくなります。暦をめくり、今の季節ではもう春を待ち遠しく感じることや、夏の終わりに切なさを感じる気分のときには、この fox のセリフを思い出すことがあります。
お笑いでいう「おやくそく」や、水戸黄門の印籠シーンなどもまたこれに入りますね。ひょっとしてこれって心理学的には何か名称がついていたりして。私がつけるなら「フォックス効果」ですね、絶対に。